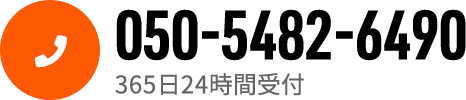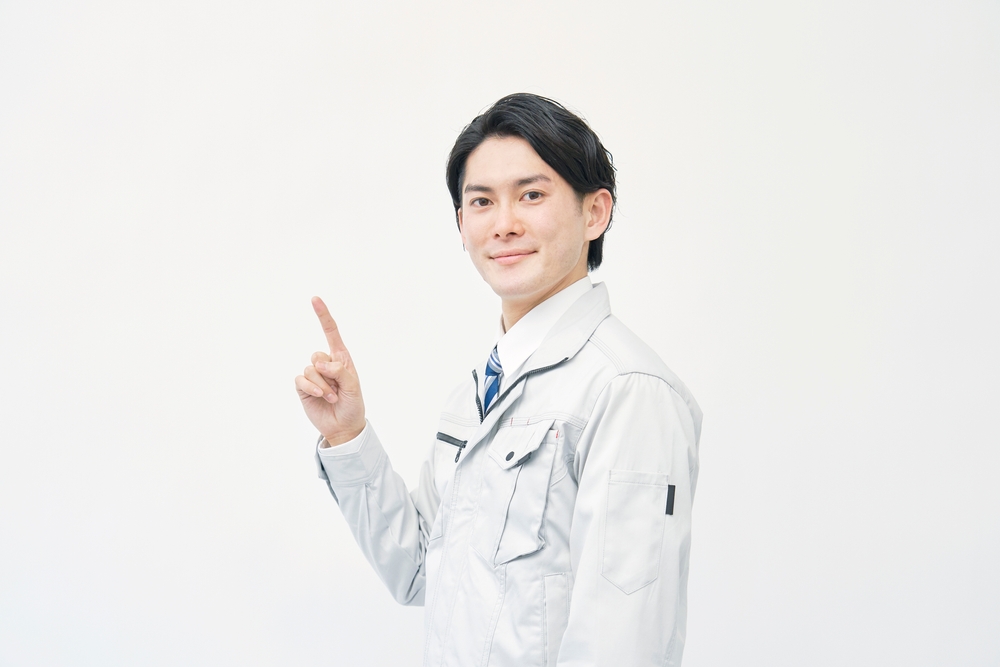この記事を要約すると...
テレビを設置する際にはテレビ端子と接続する必要がありますが、1台設置すればテレビ端子も1つ塞がってしまいます。テレビ端子が壁面に1つしかない家庭でも、2台目のテレビを設置したいと考えている方は多いでしょう。 そんな場合には、分配器を使用する方法があります。ただ、分配器にもさまざまな種類があるため、用途や環境に合わせて選ぶことが大切です。 今回は、分配器を使用して2台目のテレビを設置する方法について、他の方法とあわせて解説します。
2台目のテレビを見るには分配器を設置しよう
壁面のテレビ端子が1つのみの環境で2台目のテレビを設置する際には、分配器が必要です。ただ、分配器と良く似ているものとして「分波器」や「分岐器」という装置もあります。最初にそれぞれの装置の違いを理解しておきましょう。
複数のテレビを見るために使う「分配器」
分配器は、アンテナ端子の入力信号を2つ以上に分配する装置です。分配器の入力端子をテレビ端子に接続し、出力端子をテレビに接続します。そうすることで、壁面にテレビ端子が1つしかなくても、複数のテレビを同時に接続できる仕組みです。
分配された入力信号は、特定の出力端子に強さが偏ることはありません。どの出力端子からも同じ強さの信号が流れます。
また、分配器の出力端子の数は2つだけとは限りません。出力端子が2つのものは「2分配器」と呼ばれており、他にも「3分配器」「4分配器」などの種類があります。
ただし、分配数が多いと分配損失も大きくなる点に注意が必要です。信号の出力レベルが下がるため、映像の乱れやノイズなどが発生しやすくなってしまうからです。
BS/CS番組を見るには「分波器」を設置しよう
分波器は地デジとBS/CS放送の電波を2つに分ける装置です。衛星放送のアンテナを設置している場合には、壁面のテレビ端子からは地デジとBS/CS放送の入力信号が1本のケーブルで入ってきます。
一方で、テレビの背面には「地上デジタル入力端子」と「BS/CS入力端子」が付いているため、1本のケーブルでは接続できません。分波器によって2種類の電波を2本のケーブルに振り分けてそれぞれの端子に接続します。
大型の建物では「分岐器」が設置される
分岐器は入力信号の一部を分岐させる際に使用する装置です。分配器は入力信号を均等に分けますが、分岐器は異なる比率で出力します。例えば、2つに分ける際に9:1のような比率で出力するという具合です。
主にビルやマンションなどの大きな建物では、分岐器が壁面のテレビ端子に埋め込まれています。メインケーブルの出力レベルを落とさずに供給量を調整するためです。
分配器の選び方は?
分配器の一般的な価格帯は3,000~17,000円です。製品の性能や耐久性などにより価格に差があるため、用途や環境を考慮して選ぶようにしましょう。選ぶ際の基準は主に次の表の通りです。
| 該当 | 非該当 | |
| BS/CSを視聴する | 全端子通電型 | 1端子通電型 |
| 4K/8K放送を視聴する | 3224MHz対応 | 2071MHz対応 |
| HDDを接続する | 単体型 | ケーブル付きタイプ |
全端子通電型はすべての出力端子からアンテナへ通電するタイプで、1端子通電型は文字通り1つの端子からしか通電しません。一方でBS/CS放送を視聴するためには、アンテナへの通電が必要です。そのため、BS/CS放送を視聴するのであれば、全端子通電型の分配器を選ぶようにしましょう。
4K/8K放送は従来の地デジやBS/CSと周波数が異なるため、分配器も4K/8Kの周波数に対応している必要があります。HDDを接続する際には、単体型の分配器を使用すると、ケーブルの長さを調整できるため便利です。
また、出力端子の数に関しては、テレビの台数と同数のものを選べば当面は困ることはありません。しかし、今後テレビの台数が増える可能性も考慮し、1端子多い製品を選ぶのがベストです。
分配器の種類についてはこちらの記事もあわせてご覧ください。
「テレビの分配器とは?分波器・分岐器との違いや種類、選び方も解説」
2台目のテレビ視聴に分配器を使う際の注意点
2台目のテレビに分配器を使用する際には、次の3点に注意が必要です。
テレビ用の分配器であるか確認する
分配器という名称で販売されている装置は、テレビ用の分配器だけとは限りません。テレビ以外でも、信号の振り分けのために使用する装置が多くあり、分配器という名称で販売されていることがあります。
あまりよく見ないで購入すると、テレビ用ではないものを選んでしまう可能性もあるため注意しましょう。必ず「テレビ用の分配器」であることを確認してから購入することが大切です。
使用しない出力端子をそのままにしない
分配器に付いている出力端子のうち、使用しないものがある場合には、そのままにしておくのは避けましょう。使用していない出力端子がむき出しの状態だと、電波が漏れて他の機器に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、外部の電波が使用していない出力端子に入ってきて、テレビの映像が乱れることもあるかもしれません。
そのような事態を回避するための道具として、ダミー抵抗というものがあるため、分配器と一緒に購入しておきましょう。使用していない出力端子にダミー抵抗を装着すれば、塞がれるため、電波の漏えいや飛び込みなどを防止できます。
分配器よりテレビ側にブースターを設置しない
分配器を使用すると分配損失が発生するため、ノイズなどが多い場合にはブースターを使用します。ブースターというのは、電波を増幅させるための機器です。
しかし、ブースターを分配器よりテレビ側に接続するとかえって映りが悪くなってしまう場合があります。ノイズも一緒に増幅させてしまうためです。ブースターを使用する際には、分配器側に設置しましょう。
分配器以外で2台目のテレビを見る方法
壁面にテレビ端子が1つのみの場合、分配器を使用せずに2台目のテレビを見る方法もいくつかあります。では、どのような方法で2台目のテレビを見られるのかみていきましょう。
無線LANを利用する
無線LANにテレビを接続して、テレビ端子とケーブルで接続することなく視聴する方法があります。1台目のテレビで番組を映し、それを2台目のテレビに無線LANルーターを通じて送信するという方法です。
ただし、この方法は1台目と2台目のテレビがともに無線LANルーターに接続可能なテレビでないと行えません。
関連記事:「テレビアンテナを無線で飛ばしたい!方法や注意点を解説」
ワンセグ・フルセグを利用する
ポータブルテレビなら、ワンセグチューナーやフルセグチューナーが内蔵されています。持ち運んで使用することを想定しているため、テレビ端子に接続せずに視聴できる仕様です。
ただし、画面は小さめで画質も通常の液晶テレビと比べると見劣りしてしまいます。大きさや画質はあまり気にせず、地デジ番組を視聴できさえすればそれで構わないという方にはおすすめです。
室内アンテナを設置する
据え置き型の室内アンテナやペーパーアンテナを接続する方法もあります。室内に設置して使用できるため、テレビ端子がなくても問題ありません。ただし、屋根や外壁に設置するアンテナと比べると受信感度が劣るため映像の品質が低下することがあります。
また、ペーパーアンテナは室内アンテナの一種で紙のような薄型の形状のものです。壁や窓などに貼り付けるようにして設置できます。
室内アンテナについてはこちらの記事もあわせてご覧ください。
「室内アンテナのおすすめ5選!選び方や快適に視聴する方法も解説」
テレビ端子を増設する
内壁にテレビ端子を増設する方法もあります。ただし、テレビ端子の増設には工事が必要です。費用は建物の構造や増設場所によって大きく異なります。DIYでも一応可能ですが、あまりおすすめはできません。
テレビ端子の増設について詳しくはこちらの記事もあわせてご覧ください。
「テレビ端子の増設はDIYでもできる?方法や受信不良が起こった場合の対処法も解説」
まとめ
内壁にテレビ端子が1つしかなくても、分配器を使用すれば2台目のテレビを設置できます。分波器や分岐器など似ている装置もあるため間違えないようにしましょう。価格は3,000~17,000円程度と幅がありますが、必要な機能を考慮して選ぶことが大切です。
分配器とあわせてダミー抵抗やブースターなどが必要な場合には一緒に購入しておきましょう。
また、これを機にテレビアンテナを新しいものに交換しようと検討している方もいるかもしれません。テレビアンテナの設置を検討するなら、Go!Go!アンテナがおすすめです。テレビアンテナの修理や新規設置施工を依頼できて、地元密着型でスピーディーに対応してもらえます。アンテナだけでなく関連機器の設置にも対応しているため、気になる方は電話やLINEで問い合わせてみましょう。